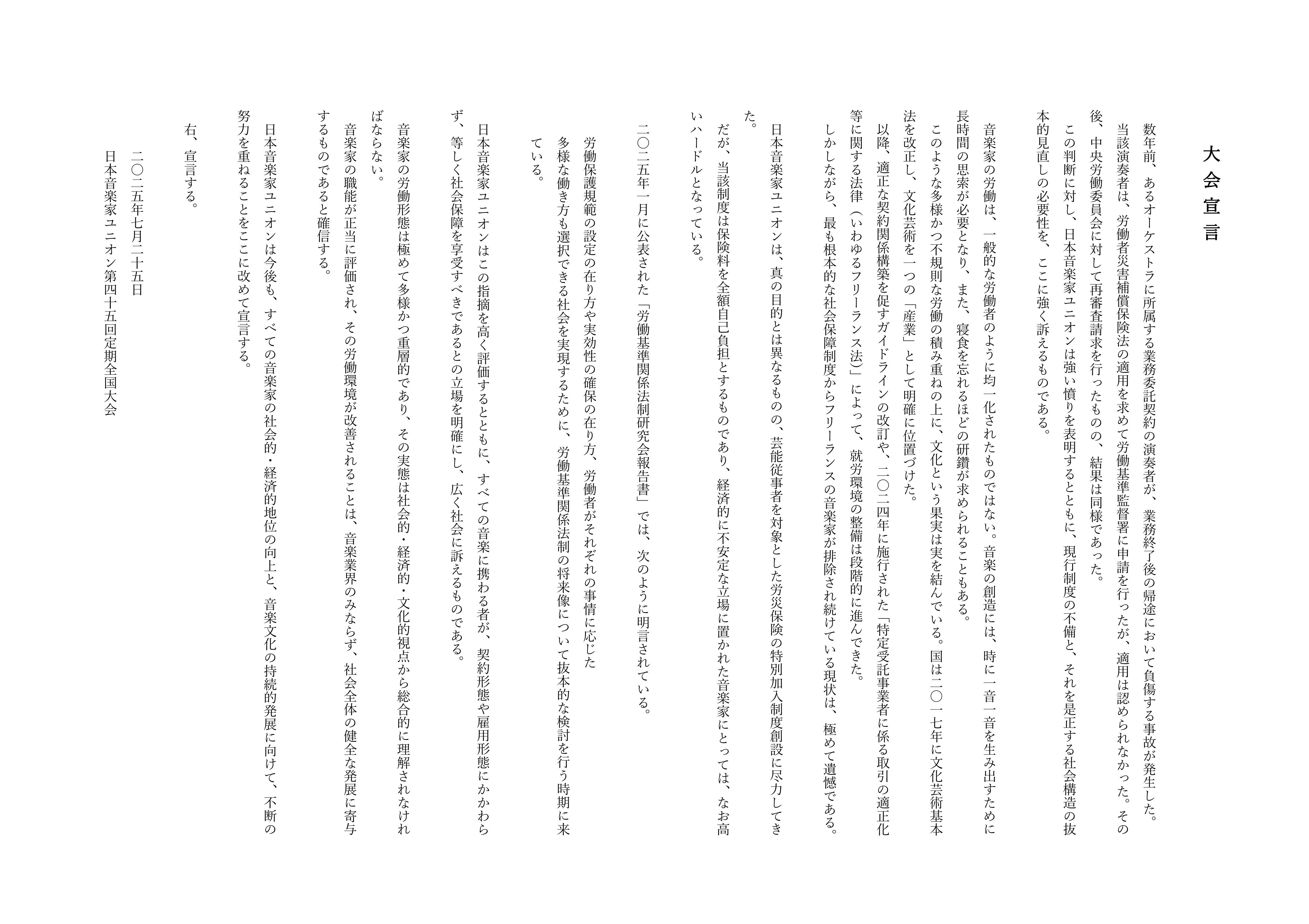
第45回定期全国大会
大 会 宣 言
数年前、あるオーケストラに所属する業務委託契約の演奏者が、業務終了後の帰途において負傷する事故が発生した。
当該演奏者は、労働者災害補償保険法の適用を求めて労働基準監督署に申請を行ったが、適用は認められなかった。その後、中央労働委員会に対して再審査請求を行ったものの、結果は同様であった。
この判断に対し、日本音楽家ユニオンは強い憤りを表明するとともに、現行制度の不備と、それを是正する社会構造の抜本的見直しの必要性を、ここに強く訴えるものである。
音楽家の労働は、一般的な労働者のように均一化されたものではない。音楽の創造には、時に一音一音を生み出すために長時間の思索が必要となり、また、寝食を忘れるほどの研鑽が求められることもある。
このような多様かつ不規則な労働の積み重ねの上に、文化という果実は実を結んでいる。国は二〇一七年に文化芸術基本法を改正し、文化芸術を一つの「産業」として明確に位置づけた。
以降、適正な契約関係構築を促すガイドラインの改訂や、二〇二四年に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(いわゆるフリーランス法)」によって、就労環境の整備は段階的に進んできた。
しかしながら、最も根本的な社会保障制度からフリーランスの音楽家が排除され続けている現状は、極めて遺憾である。
日本音楽家ユニオンは、真の目的とは異なるものの、芸能従事者を対象とした労災保険の特別加入制度創設に尽力してきた。
だが、当該制度は保険料を全額自己負担とするものであり、経済的に不安定な立場に置かれた音楽家にとっては、なお高いハードルとなっている。
二〇二五年一月に公表された「労働基準関係法制研究会報告書」では、次のように明言されている。
労働保護規範の設定の在り方や実効性の確保の在り方、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方も選択できる社会を実現するために、労働基準関係法制の将来像について抜本的な検討を行う時期に来ている。
日本音楽家ユニオンはこの指摘を高く評価するとともに、すべての音楽に携わる者が、契約形態や雇用形態にかかわらず、等しく社会保障を享受すべきであるとの立場を明確にし、広く社会に訴えるものである。
音楽家の労働形態は極めて多様かつ重層的であり、その実態は社会的・経済的・文化的視点から総合的に理解されなければならない。
音楽家の職能が正当に評価され、その労働環境が改善されることは、音楽業界のみならず、社会全体の健全な発展に寄与するものであると確信する。
日本音楽家ユニオンは今後も、すべての音楽家の社会的・経済的地位の向上と、音楽文化の持続的発展に向けて、不断の努力を重ねることをここに改めて宣言する。
右、宣言する。
二〇二五年七月二十五日
日本音楽家ユニオン第四十五回定期全国大会